石垣島の名蔵川の河口一帯を名蔵アンパルと呼ばれています。マングローブ林と広大な干潟があり、そこには八重山特有の動植物が生息しています。
この素晴らしい「海のゆりかご」と言われている名蔵アンパルについてご紹介します。
名蔵アンパルへのアクセス
市街地から車で約15分ほどで行くことができます。県道79号線を北上し、名蔵大橋を渡ると無料の駐車場があります。

そこから下に降りていくと、名蔵大橋の下にいくことができます。二カ所降りるところがありますが、急な坂でロープもあるので気を付けてください。またどんな生物がいるか看板を確認してから行くと楽しさも倍増になります!

潮の干満で奥まで行ける時と、長靴や濡れても良い靴でないと厳しい時があります。生物の観察であれば、干潮の時に合わせていくようにしましょう。
アンパルの近くにはやいま村やみんさー工房みね屋さんもあります。寄り道しながら観光も楽しいですね!
ミンサーの記事はこちら👇
名蔵アンパルのラムサール条約登録
石垣島最大の湿地アンパルは、2005年(平成17年)に水鳥の生息地として重要性が認められ、ラムサール条約の登録湿地となりました。
県内では最も多種の野鳥が訪れるマングローブ林と干潟として知られるようになり、また、市民の環境保全意識も高まっています。
マングローブ林を構成する植物

ヤエヤマヒルギ、オヒルギ、ヒルギモドキ、シマシラキなどの木本類と、ソナレシバ、ミルスベリビユなどの草本類などです。
ミルスベリビユは方言でイミズナーと言い、各地域の豊年祭で使用する貴重な植物です。

また、マングローブの生息地の特徴として、亜熱帯、熱帯地域の海水と淡水が混ざり合う特別な環境で育ちます。
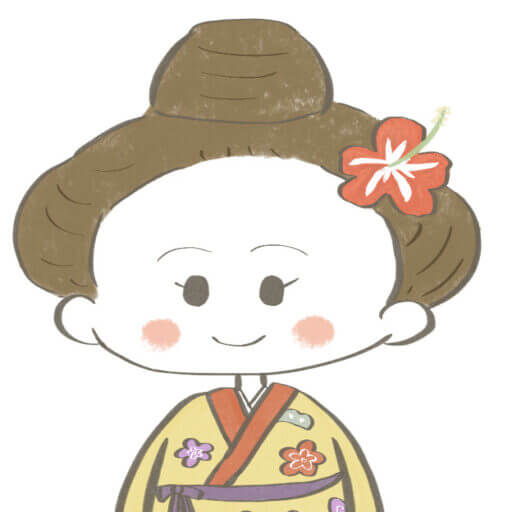
マングローブは湿地に生えています。不安定な場所で支えるためと、土の中の酸素が少ないために、このような根になりました。
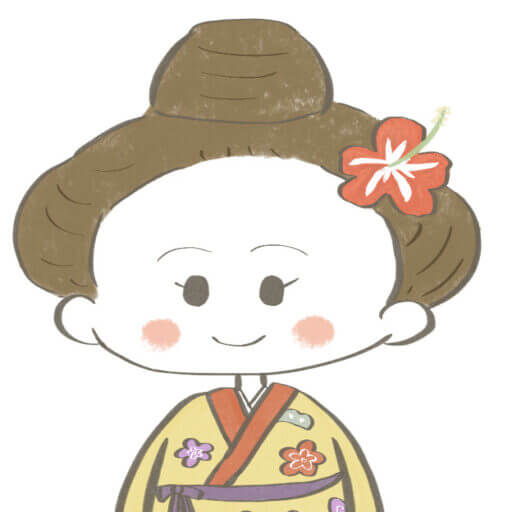
海水でも生きていけるのは、塩分を葉にためて落葉させるなど、塩分を排除する機能があるためです。驚きですね!
アンパルで見られる水辺の生物
アンパルでよく見つけることができる生き物を紹介します。

他に、ミナミコメツキガニ、ベニシオマネキ、ノコギリガサミなど多種多様なカニが生息しています。
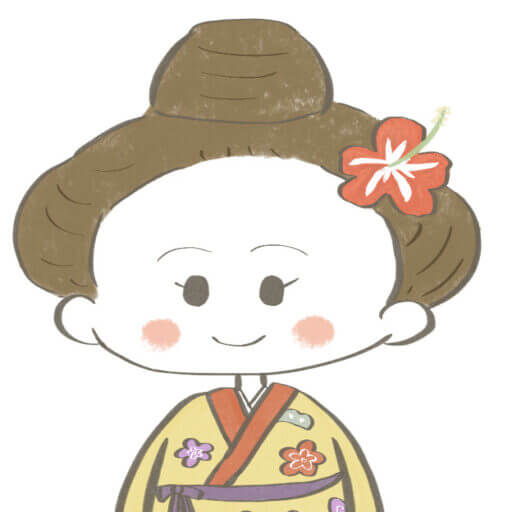
びっくりするほど、ウジャウジャーとシオマネキがいるのですが、人が少しでも近づくと一瞬にして砂穴にもぐりこみます!
アンパルは、15種類のカニの生態や特徴をとらえたユーモラスな動きを歌った民謡「アンパルヌミダガーマユンタ」の舞台となってるゆかりの地でもあります。
上記の民謡を基に「あんぱるぬゆんた」という絵本が出版されており、石垣島の小学校でとてもよく親しまれています。

トントンミーという愛称でよばれている「ミナミトビハゼ」。

ヒルギの葉を食べるキバウミニナ。
このキバウミニナは、大きさ10㎝ほどで、マングローブに生息する最大の巻貝です。
マングローブ林に生息し、その固い落ち葉を食べ、分解しているため、マングローブの生態系の中で、重要な役目を担っています。
耳をすませば、この貝が落ち葉を食べる音が聞こえます。
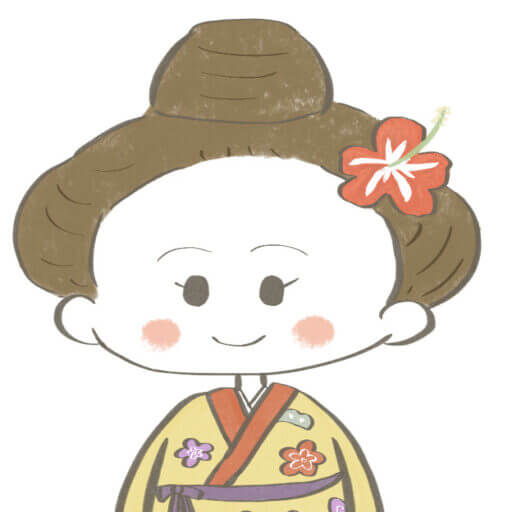
キバウミニナの中を見るとヤドカリが入っている場合が多いです。このヤドカリを殻からとって釣りをする人もいます。マングローブジャック(ゴマフエダイ)、チヌなどが釣れるそうです。
ゴマフエダイは方言でウルアカナー、カースビーともいいます
アンパルの鳥類
名蔵アンパルで見られる鳥類は、越冬する冬鳥や渡り鳥など、多様な鳥が生息しています。
また、キンバト、リュウキュウコノハズク、カンムリワシ、アカショウビンなど沖縄固有の鳥も見ることができます。
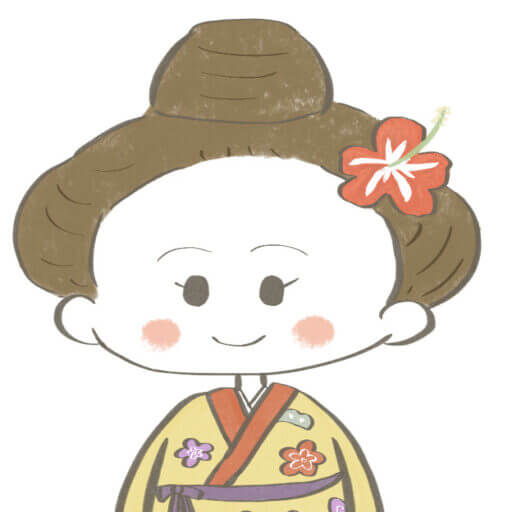
名蔵アンパルはバードウォッチングにも最適ですね!
鳥たちを警戒させないように、双眼鏡などで離れた所からみるようにしましょう。
アンパルでの注意点
多種多様な生物を育む名蔵アンパルですが、ゴミの不法投棄が目立っています。
また、海水温の上昇により、オキナワアナジャコの塚が消失したり、オヒルギの林が衰退しているところもあります。
アンパルで生物観察をしたときのゴミは持ち帰り、岩や石を動かした場合は元に戻してくださいね。
サンセットや星空が美しい名蔵アンパル
色々な生き物が観察できる昼間のアンパルも面白いですが、名蔵大橋から日が海へと沈んでいく様子もとてもきれいです。
また、夜は満天の星を楽しむことができます。

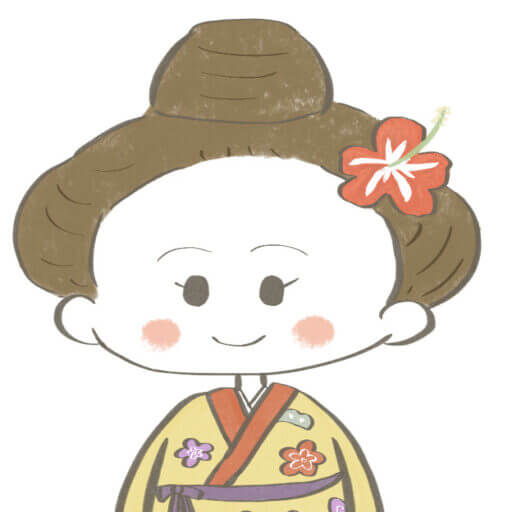
マングローブ干潟は海からも山からも影響を受けやすいです。
豊かな自然を守っていきましょう。
名蔵近郊のスポット
石垣島旅行はじゃらんで♪
スカイチケットで航空券ゲット!
安全安心なJTAB


