昔ながらの梅干し
梅干しが大好き!昔は母親が梅干しを作っていましたが、
自分はズボラなので、買えるものはスーパーで買っていました。
でもいい梅干しは高い!そして、お安めのは色んなものが入ってそう。しかも甘め。
友人宅で頂いた自家製の梅干しに感動し、自分でも作ってみることにしました。
また、自分で作ることは、安心安全プラス生産者に応援でき、環境にも優しいです。
梅と容器等とその他必需品の購入
友人のお勧めでこちらから買いました。↓

規格外のもので 12㎏ ¥7,800です。友人と半分にして6キロの梅を使います。
かなりお安い!
大きさバラバラでキズや斑点がありますが、問題なく使えます。
大分県産の南高梅。外国のものではなく日本産を選びました。
梅を注文5月の下旬にしました。
あっという間に売れてしまうのでもう少し、早めのほうがいいかもしれません。
梅が届くのは6月上旬。その間に、梅干しに必要なものを揃えました。
できるだけ家にあるものを使おうと↓を使うつもりでしたが、

これだと、干している時に梅がころがってしまうかもしれないのでいけないと言われました。
結局こちらを購入!↓
これなら、6キロ分を干すことができるそうです。フード付きっていうのもうれしいです。
あとホームセンターで漬けものの容器15L(中ブタ付き)とおもしを購入
容器は梅の約3倍程度のものがいいらしいです。私のは3倍弱です。おもしは5キロと2.5キロを準備。
友人はペットボトルに水を入れておもしにしていました(なるほど!)
他に大切なのは塩!「瀬戸のほんじお」を使用。粗塩が初心者には適しています。
焼酎の代わりに泡盛の4合瓶を購入。
竹串、ふきん、ボウルなど。(結構こまごまと必要でした)
あと梅干しを入れる保存瓶。5ℓのガラスの保存瓶を準備しました。
梅の塩漬け
6月上旬に届いた青梅は、少し黄熟しかかっていました。(梅干しの梅は黄熟のものを使用)
1日か2日ですべて黄熟したので早速塩漬けです(6月14日)
6キロに対して17.5%の塩を準備。本では18%でしたが、少し減塩。

まだ、少し青いものとキズが深いものを分けました。
キズのものはグラニュー糖を入れて梅酵素にしました。
ここから、写真がないのですが
・梅をやさしく流水で洗う・梅のヘソの部分を竹串でとり、
ふきんで水けをふきとる(かなりしっかりと)
・アルコール消毒した容器の底に塩をひとつかみして平均にふる。
・焼酎(泡盛可)をボウルに入れて、梅を適量入れてころがしながらまぶす
・まぶした梅を容器の底にひとならべして多めの塩をふる
・そのまま、梅、塩、梅と順に繰り返して漬け込む
(塩はうえにいくほど多くふる)
・残った塩を全部ふって、熱湯消毒した中ぶたをのせる
・熱湯消毒したおもしをのせる。黄熟してるなら、梅とほぼ同じ重さにする。
・新聞を2枚重ねて紙ブタをして、日付を書く。
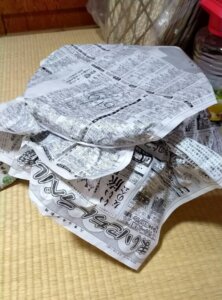
白梅酢が上がってきたらおもしを減らし、白梅酢をとる

透明な白梅酢があがってきました。二日ほどで結構あがってきます。
カビがないか毎日みて、みつけたらすぐ取り出します。
運よく全くカビませんでした。白梅酢は10日ほどたったものが一番良いらしいです。梅の上から2cmを残して余分な白梅酢をとり、保存しました。↓

背景汚くてすみません。(購入したザルや保存瓶も映っています 笑)
常温で放置していたら、茶色になってしまいました。
変色を防ぐには色付きの瓶に入れるか、冷蔵庫保存にするかの方法があります。
常温でも品質的には大丈夫ですが、変色しやすくなります。
おもしは5キロから、2.5キロに減らしました。
赤じそ漬け
赤ジソが出回る時期(6月中旬から7月上旬あたり)になったら、
スーパーなどで早めに買ってください。
私はその時期を逃してしまったのか、売っている場所を探せなかったのか、購入できませんでした。
結局市販の「赤ジソ漬」を1キロ購入。ちなみに5キロに対して赤ジソは1キロです。
私は少し少な目にしました。
次年度は生の赤紫蘇を手に入れたいと思います。
生の紫蘇が手に入ると赤紫蘇の副産物(シソジュース)なども作れるからです。
でも市販品は楽チンでした♪ 手間をかけたくない方は逆にこちらのほうがいいと思います。
お好みの赤ジソでいいと思いますが、私は↑を買いました。
塩漬けにされている梅に 市販の赤ジソ漬けを汁まですべて入れて、中ブタを入れておもし
をします(梅の半分の量:6キロの梅だと3キロですが、2.5キロのおもしにしています)
そのまま 時々、カビていないか確認しながら、干す日までそのままにしておきます。
冷暗所の置くそうですが、私は普通に居間に置いていました。

↑干す前日の状態です。
土用干し
土用干しは7月20日~8月7日あたりの
晴天が4日続く日を見極めて干します。
台風がウロチョロしていたので、8月11日に干すことになりました。
1日目(晴れ)

赤ジソを絞ってボウルにとりだして、
日光があたる場所に干しました。赤梅酢の容器も一緒に日光にあてます。
コンクリートの上に直に置くのではなく、段ボールの上などおいてください。
通気性があったほうがいいです。
梅干し同士がくっつかないように置いたら、全部干せなくなり
急遽、小さいザルがあったので使用しました。
そのまま日光があたる場所に変えながら、9時から16時まで干しました。
12時ごろに1回裏返しをしました。

夕方小さい梅干しをひとつ食べたら、もう立派に梅干し!

そして16時ごろ干した梅を再び梅酢に戻しました。

おもしをしないせいか、梅酢にすべて浸かりませんが、一応ざっくりとでもついていたらいいそうです。気になって私は白梅酢を後から投入しました。
2日目(曇り)
晴天の予定が曇りでした。
でも石垣島は強烈な日差しなので、半日影ぐらいがちょうどいいと聞きました。
日中に一度裏返し。
1日目よりは干しあがりがイマイチのまま翌日までそのまま干しました。
夜露にあてることで、ふっくらした梅干しになります。
*基本的に曇天、雨天の時は外に出さずに家の中に置いておきましょう。
*容器の中の赤梅酢はザルやフキンでこして、色付きの瓶に入れます。
常温でも大丈夫ですが、色を気にするなら冷蔵庫で保管してください。
3日目(雨のためカウントせず)
まさかの雨。天気予報みていましたが。とても天気もコロコロ変わり、
外に出しては中に入れていましたが、結局あきらめて途中で家の中に入れました。かなりの疲労。
曇天や雨天の場合はあきらめて家の中にいれるべきです。

私には↑の梅干しはとても美味しくて終了!と思いましたが、もう一回
干して夜露にあてたら、さらに皮も柔らかく美味しくなると聞いたので、天気をみて
再びチャレンジしたいと思います。
天候不順に振り回されて予定と変わり右往左往!
自然相手では仕方ありません。毎年、梅干しの味は変わるとはこういう事なんですね!
3日目(晴れ)
朝の天気は微妙でまたしても、右往左往していましたが午後からは無事晴れました。
いい感じに干せて塩の結晶もみえました。
そのまま夜露にあて翌日の午前中に取り込んで終了。完成です。
さらにカラっとしたい方は干し加減をみながらお好みの
ところまで干しましょう。
干しすぎるとカラカラになるので要注意です。

まとめ
初めての梅づくりで感じたことは
・必要な準備を前もって揃える(梅はすぐ黄熟します)
・最初はマニュアル通り行う(塩分、おもしなど)
・天候をきちんと見極める(大事です)
・干す→梅酢に戻す→干す→夜露→干す→夜露
を基本にすると皮も柔らかくなります。
完成した梅は、我ながら美味しくできたと思います。
梅づくりをした人のみ味わえる喜びです。
赤梅酢や紫蘇をまた違う形で利用できるのも楽しみになります。
こちらの記事(赤梅酢の利用)もご覧くださいね!
